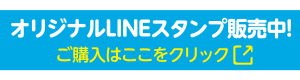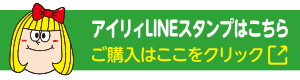11Oct

子育てで、つい子どもに向かって言ってしまう言葉がある。
「周りの人に迷惑をかけないようにね」と。
そういうことは保護者が注意しなきゃ、保護者が教えていかなきゃ、と思ってしまうところがあるのだけれど、この前読んだ、鴻上尚史さんの本『コミュニケイションのレッスン』(だいわ文庫)の中で、「周りの人に迷惑をかけないようにね」と子どもに教えることが果たして本当にその子どものためになるのか、ひいては社会を構成していく大切な一人である子どもに、その発達段階を理解しようとしない接し方をしていて本当にいいのだろうか?という思いが芽生え、「確かにそうだよね」と共感できるところがあったので、こちらで紹介します。
「交渉する」力が落ちていることの理由のもうひとつは、「人に迷惑をかけない」という育て方が大きいのじゃないかと僕は思っています。
「人に迷惑をかけない」という言葉は、「何がその人の迷惑になるのか」が明確に分かっている人が使う言葉です(もちろん、「盗まない」とか「人を殺さない」という基本的なことは別です。「迷惑をかけない」という言葉には、もっと精神的な「気配り」の要求を感じます)。
『コミュニケイションのレッスン』(鴻上尚史・著/だいわ文庫)
鴻上さんがおっしゃるには具体的には「転んで泣いている子供に手を出して立たせた方が迷惑なのか、そのままにした方が迷惑なのか、市販のお菓子を取り上げて食べさせない方が迷惑なのか、市販のお菓子を食べさせた方が迷惑なのか、そこをはっきり分かっている人が使う言葉」であって、「人に迷惑をかけない」というのはお互いが共通の価値観で生きている「世間」の中で通用するルールなのだと。
それは、一度、実社会に出て、ビジネスの現場に立てば、そこは「社会」で、何が迷惑でなくて何が迷惑か分からないのが「社会」というところなのだと。
こっちの都合と相手の都合がぶつかり、これはあきらかに相手の迷惑になるのだけれど、そうしなければこっちの商売が成り立たないとか、相手の都合を考えていたらこっちはあきらかに迷惑だとか、よかれと思ってやったことが相手にとってはとても迷惑だったとかー共通の価値観がない現場を知ると、簡単には、「他人に迷惑をかけない人」が子育ての一番の目標にはできなくなるのです。
小さい頃から「他人の迷惑にならないように」と教育された子供達が大きくなって、ビジネスや組織の現場で、価値が対立するコミュニケイションに飛び込むだろうかと僕は考えます。相手と対立し、相手の提案を拒否することは、「相手に迷惑をかけること」だと思うんじゃないかと心配するのです。
『コミュニケイションのレッスン』(鴻上尚史・著/だいわ文庫)
なるほど!会社の(社会の)人間関係で難しく感じるところは確かにここにあります。
少し考えれば違う気もするけれど、「他人に迷惑をかけない」という強烈な刷り込みが頭から離れない。だから、最初からなるべく交わらないようにしよう。コミュニケイションは最低限に押さえて、自分のやるべきことだけをやろうーそう結論するのはある意味、自然な流れのような気がします
『コミュニケイションのレッスン』(鴻上尚史・著/だいわ文庫)
それから、この本はこう続きます。
【人は一人では生きていけない】
「人は人と交わらなければ生きることはできない。問題は、それを迷惑と感じるか、お互いさまと感じるかだけだ」という言い方があります。
「迷惑」と「お互いさま」は、同じ行為をどう見るかだけの違い、ということです。
『コミュニケイションのレッスン』(鴻上尚史・著/だいわ文庫)
この、「どう見るか」というところ。「迷惑にならないように」を考えることも大切ですが、できないこと、時間がかかること、わからないことに対して「お互いさま」の氣持ちを持てるといいですね。
もともとこの言葉は、誰にも相談せず思い詰めて自殺を試みた人とか、一人抱え込んで病気になってしまった人とか、いつも人と距離を置いて孤独をこじらせてしまった人に向けてのものです。
人は一人では生きていけません。具体的な意味で、一人では生きていけないのです。どんなに孤独に耐えていると思っても、どこか精神のバランスは危うくなっていすはずです。
まして。職場やクラス、家庭など、周りに人がいるのに、一人で誰にも頼らず、迷惑をかけないで生きていこうと思ったとしたら、その決意はかなり周辺の人々を混乱させているか、振り回しているはずです。
苦しい時に苦しいと言うから人間は生きていけるのです。困ったときは困った、助けて欲しい時は助けて欲しいと言えるから人間は精神のバランスが取れるのです。
ストレスに強い人とは、一人で抱え込む人ではなく、うまく周りの人と話すことで発散できる人なのです。
『コミュニケイションのレッスン』(鴻上尚史・著/だいわ文庫)
「周りに人がいるのに、一人で誰にも頼らず、迷惑をかけないで生きていこうと思ったとしたら、その決意はかなり周辺の人々を混乱させているか、振り回しているはずです。」というところには、その逆を思ったことはありますが、実は、周囲の人を混乱させたり、振り回していたりするのは、一人で誰も頼らず、迷惑をかけないで生きていこうという決意の方が、返ってそういう結果になっている、という指摘に目から鱗の思いでした。独りよがりや独り相撲、空回りという言葉があるのは、そういったところからも言えるのかも知れませんね。
苦しい時に苦しいと言うのは、迷惑ではありません。お互いさまです。苦しいと言ったあなたは、次は相手の苦しいと言う言葉を聞けばいいのです。人間はそうやって助け合って生きるのです。
あなたが濃密な「世間」に生きているのなら、積極的にその人たちに頼るべきです。そして、次に相手が苦しい時は、同じように積極的に受け入れればいいのです。それは「迷惑」ではなく、「お互いさま」です。一生、ケガもせず、精神も落ち込まず、体力も失わないと確信を持って断言できる人だけが、この「お互いさま」の輪から飛び出せばいいのです。
『コミュニケイションのレッスン』(鴻上尚史・著/だいわ文庫)
鴻上さんがこの本の中でおっしゃっていること、心に刺さりました。これは、まだ20代、30代、40代前半でも本当には理解できていなかった氣がします。親に対して、身内に対して、特に厳しく見ていた氣がします。心のどこかで、「私はそんなことしない」「そうならない」「私はちゃんとできている」という思いがあったら、自分の心の中のそんな声を聞き逃さないで拾って、自覚したら、「お互いさま」を本当に知ることが出来るようになるのかな。年齢を重ねて、自分自身や周りを見て、ようやく、そのことに氣づきが持てるようになってきたように思います。
子どもを「しつけなきゃ」と思っていると、「人様に迷惑をかけないように」そして「何でも自分でできることは自分でできるように」とついそちらの方を強く子どもに求めてしまっていくようになっていて、もしかしたら、そうではなく「お互いさま」、「時間がかかってもいいんだよ」「できないことは無理をせず、お互いに苦に感じないで出来ることを助け合えばいいんだよ」という姿勢も、子どもに教えるときに持ち合わせたい思いです(子どもの諦めないで挑戦したり、時間がかかっても出来るようになるまでやってみたいと思う氣持ちは尊重したいと思います)。もちろん、子どもがいるところだけではなく、日常生活の人間関係の中で忘れないでいたいところ。
そして、そのときの伝え方まで、具体的に書いてくださってます↓。
もし、あなたが薄い「世間」に生きているのなら、苦しい時に苦しいと言う時、あなたのできる範囲でポジティブに語ることが重要です。微笑みながら言う必要はありません。ただ、(中略)あなたができるギリギリのポジティブな言い方や表情で、苦しいと語ることが大切なのです。
生きていることが辛いと、それでも前を向きながら語ること。なんとかしたいと思いながら悲鳴を上げること。
『コミュニケイションのレッスン』(鴻上尚史・著/だいわ文庫)
先日、西洋占星術家のマドモアゼル・愛さんのYouTube番組「年内残り3ヶ月で新しい交友を作っておきたい」を聞いていて、同様のことを語っていらっしゃいました。
どうやって俺たちさ、生きていこうかなと、深刻ではなく、深刻になる前に情報を共有しあって、良い意味で赤裸々に自分の氣持ちを語れる人を最低でも一人、二人、三人と持てば、ずいぶん心強いことになっていくという風に思います。
西洋占星術家のマドモアゼル・愛さんのYouTube番組「年内残り3ヶ月で新しい交友を作っておきたい」より
未来について、友達と、知り合いと、また、考えを同じくするような者たちと語り合うことがとっても大事だなというような氣がしてなりませんとおっしゃっていたところに共感しました。
鴻上さんはこう締め括ります。
「人に迷惑をかけない」生き方を目指すのではなく、「あなたと人が幸せになる」生き方を目指すのです。
『コミュニケイションのレッスン』(鴻上尚史・著/だいわ文庫)
PR

コミュニケイションのレッスン (だいわ文庫)